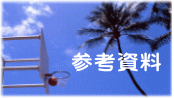クリティカルシンキング 
クリティカルシンキングのルーブリック:2014.9.15 評価規準は、「自分の考えの構築」と「学問的知識・専門家の主張の考察」の二つをAからHまで連続的 にレベルで分けて、評価指標で示しています。
2015年春学期「初等教育学専修ゼミ1」では、「思考力育成法」をテーマに授業を行って、中間と最終レポートの提出を求めています。そこで養われる力は、今や高大連携の中核をなすと言われているクリティカルシンキングです。このホームページを活用してよりよいレポートを作成して下さい。
【クリティカルシンキングを活用した2014年度のレポート例】
課題:教師中心と子ども中心の教育実践についてそれぞれの長短所を踏まえて、どのような実践が望ましいと思うのかを論じなさい。
執筆条件:
①あなたの主張を初めに示した後、「どうしてそう考えるのか」という論拠を授業中に配布した資料や視聴した内容だけでなく、自分の経験や別途調べた事柄とも関連付けて、このような「学習活動」や「時間を設ける」のように、具体的に論じる。
②必要と思えば、図やイラストなども描いたり、引用して、相手が「なるほど、そうだ」と思えるような工夫も凝らすこと。
③結論をより説得力があり、強固なものにするために、自分で調べた文献資料を最低一つ組み込んでいること。
<重要な教育用語>
子ども中心の教育実践の特徴
1.子どもの学習の個別化
i)興味関心のそって理解し、追究
ii)子どもたちの授業への参画、深い教材研究
2.教師の指導の個別化
i)教師はファシリテーターの役割
ii)授業の複線化
→全員共通の題材について探究する際に、何を誰と、どのように解決するかについて個々の子どもが決めるため、
一人ひとりの学びの道筋が異なっている。
iii)実際に何の学習活動をするかを決める
教師中心の教育実践の特徴
1.言葉の吟味、学び続ける
子どもの学びを厳しく組織
2.言葉の意味の具体例を示しつつ説明
資料内容を分かりやすく解説
3.子どもに伝えたい明確なものを持つ
授業案通りに進めなくてもよい
複数の事例を示す
林竹二の教育論
a.ソクラテスの問答法をもとに、学びの組織化の概念を提唱する。
無知=知ったかぶり(世間で言われる説を鵜のみ)
知ったかぶりからの解放(本当に求めることを知る)=学問の課題
教育・・・世間の節の「吟味」(質問→意見→意見の吟味の繰り返し)
子どもの「知ったかぶり」の知識からの解放→多方向からの教師の説明→学問の深い知識
→正解でもさらに発問→本当に「自分のものか」
【クリティカルシンキングアップのための参考資料】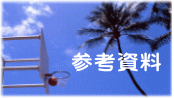
クリティカルシンキングを働かせているかどうかは、上記のルーブリック(後ほど部分的修正の可能性有り)にそって行います。でも、このような表では、抽象的で分かりにくい、具体的な例が欲しいでしょう。そのような人のために、これまでのレポートの中から該当例を掲載しました。「このように書けば、ここで記したレベルまでは到達」ということが分かると思います。「参考資料」のアイコンをクリックして、具体的なイメージ化を図り、あなたのよりよいレポートづくりに生かして下さい。